<目次>
1.はじめに
2.現状分析と問題意識
3.農政ビジョン2040
4.7つの提言
5.結び
1.はじめに
世界的な異常気象の頻発と世界人口の爆発的な増加等により、地球規模での食料危機を懸念する声がある。このような状況の中、我が国の食料自給率は低下の一途を辿り、2018年度の自給率は37%と過去最低を更新した(注1)。農水省が掲げる「食料自給率45%を目指す」という目標(注2)は完全に形骸化し、まさに今この国の農政は向かうべき方向を見失い、混迷を極める状況にある。この原因は個々には色々あるが、帰するところ国家の未来を拓く長期的展望に欠けるものがあるのではなかろうか。
本レポートでは、有事にも国民の胃袋を満たすことのできる食料自給国家の実現に向けて、20年後の2040年にあるべき日本の農業の姿として「農政ビジョン2040」を提示するとともに、その実現のための7つの具体的方策について提言したい。
注1.農業協同組合新聞「過去最低の自給率 大きい目標との乖離」,(2019.8.7)
注2.農林水産省「日本の食料自給率」,(2021.8.18閲覧)
2.現状分析と問題意識
(1)迫りくる地球規模の食料危機
国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、昨年8月に「温暖化による干魃(かんばつ)等の増加で2050年に穀物価格が最大23%上がる恐れがあり、食料不足や飢餓のリスクが高まる」と警告する特別報告書を公表した(注3)。また、現在約77億人の世界人口は今後も爆発的な増加を続け、2050年には98億人を突破すると推計されており(注4)、元シドニー工科大学教授のジュリアン・クリブ氏は21世紀の半ばに向けて人類は有史以来最も深刻な地球規模の食料危機に直面すると警鐘を鳴らしている(注5)。
これまで日本は、経済力を背景に食料を海外から大量に輸入することで豊かな食生活を維持してきたが、今後日本の経済力は相対的に低下を続けるであろう。シーレーンの破壊等によって、物理的に輸入が途絶える事態も想定される。近い将来、日本が海外から十分な食料を輸入できなくなる時代が来ることを、私たちは現実に起こりうる問題として真剣に考えなければならないのである。
注3.SankeiBiz「温暖化で穀物価格23%上昇 国連IPCC、2050年見通し警告」, (2019.8.12)
注4.国際連合広報センター「世界人口推計2019年版」,(2021.8.18閲覧)
注5.ジュリアン・クリブ(2011)「90億人の食糧問題」シーエムシー出版,p.1,p.5
(2)低下を続ける我が国の食料自給率
我が国の食料自給率(カロリーベース)は、1960年の79%(注6)をピークに年々低下の一途を辿り、2018年には37%(注7)と過去最低を更新した。このまま何もしなければ、自給率は14%程度にまで減少するとの試算もある(注8)。
食料自給率が低くても、海外から食料を輸入すれば問題ないと考える人も多い。たしかに、平時においては自給率が低くても国民生活に影響はなく、私たちは輸入品の恩恵として豊かな食生活を享受している。このこと自体は、リカードの比較生産費説や国際分業の観点からも安易に否定的に捉えるべきものではない。自給率が低いことで問題が生じるのは有事の時、すなわち海外から食料を輸入できなくなった時に初めて致命的な問題が顕在化すると言える。食料自給率に関する議論の本質は、有事の際に海外から食料の輸入が途絶えた場合、国民の胃袋をどれだけ自国で満たすことができるかという点にあることをここで強調しておきたい。
注6.農林水産省「平成22年度 食料・農業・農村白書 全文」,2010,巻末付録,p405
注7.農業協同組合新聞「過去最低の自給率 大きい目標との乖離」,(2019.8.7)
注8.菅正治(2020)「平成農政の真実 キーマンが語る」筑波書房,p.75
(3)食料自給力指標と緊急事態食料安全保障指針
有事の食料安全保障を考える上で、農水省は2015年から「食料自給力」の指標を毎年公表している(注9)。これは、我が国の農林水産業が有する潜在生産能力(農地・農業者・農業技術)をフル活用することで得られる供給可能熱量(カロリー)を試算したものであり、全ての農地で高カロリーな作物(米・小麦・いも類等)を中心に作付けすることを想定(栄養バランスは考慮)したものである(図表1)。
従来の食料自給率(カロリーベース)では、分母となる供給熱量(2019年度は2,426kcal/人・日)の中に、必要以上に摂取された過剰な食料や廃棄された食料も含まれているため、これらを除くと実際の自給率はもっと高くなるとの指摘があった。そこで、食料自給力指標では、人間が生きていくのに必要とされる推定エネルギー必要量(2,168kcal)を基準にしており、これを分母とした2019年度の食料自給率は42%となる(注9)。たしかに自給率は少し上がるが、いずれにしても十分な自給率には到底及ばないことは言うまでもない。
2019年度の食料自給力指標によると、「米・小麦中心の作付け」では平均的な1人当たりの推定エネルギー必要量の約81%(1,754kcal/2,168kcal)しか賄うことができないのに対し、「いも類中心の作付け」にした場合には推定エネルギー必要量の約120%(2,594kcal/2,168kcal)と十分なエネルギーを賄うことができる試算となっている(注9)。
有事の具体的対応として示されているのが農水省の「緊急事態食料安全保障指針」である(注10)。この指針では、レベル0~2の事態に応じて対応が分かれており、最も深刻なレベル2の事態(1人1日当たり供給熱量が2,000キロカロリーを下回ると予測される事態)では、高カロリー作物(米・小麦・いも類等)への生産転換の実施が定められている(図表2)。すなわち、上述の食料自給力指標に基づいて「米・小麦中心の作付け」、もしくは「いも類中心の作付け」に生産転換することで有事の際にも国民の胃袋を満たすことができるというものである。


注9.農林水産省「日本の食料自給力」,(2021.8.18閲覧)
注10.農林水産省「緊急事態食料安全保障指針」,(2021.8.18閲覧)
(4)食料自給国家の実現に向けた3つの課題
食料自給国家の実現に向けて、大きく3つの課題を指摘することができる。
第1に、生産資材の不足である。食料自給力指標の試算に当たっては、「肥料、農薬、化石燃料、種子、農業用水、農業機械等の生産要素は十分な量が確保されている」との前提が置かれている(注11)。しかし、我が国の農業生産資材の原料は、肥料で約93%、農薬で約38%を輸入に依存しており(注12)、食料輸入の大半が途絶えるような緊急事態において、大半を輸入に依存する肥料や農薬を十分に確保することは非現実的である。特に、化学肥料はその原料であるりん鉱石が中国・米国・モロッコ及び西サハラで、塩化加里がカナダ・ロシア・ベラルーシ・ドイツで産出量の大半を占めており(注13)、国内で自給することは難しいであろう。化学的に合成された肥料や農薬を用いない有機農業においては、慣行栽培よりも収量が減少する。具体的には、慣行比で米は81%(注14)、小麦は約5割~7割(注15)、ジャガイモは47%程度(注16)の収量となる。特に、ジャガイモは殺菌剤を使用しないことで疫病が発生すると、収量が激減するリスクがある(注17)。日本の有機農業の取組面積の割合は、0.5%(2018年)とごく僅かであり(注18)、肥料や農薬を使用できないことを考慮すると、前述した食料自給力指標は農水省の試算より大きく減少することとなる。すなわち、有事の際に生産転換を行っても、国民を飢えから守ることはできないのである。
第2に、農地の不足である。我が国は、人口に比して国土面積があまりにも小さく、かつその国土の71%が住宅地や農地として活用することができない山岳森林地帯となっている(注19)。農地面積は、1961年の608.6万haをピークに(注20)、2020年には437.2万haまで減少した(注21)。この間に造成された110万haの農地を含めると、この60年余りで失われた農地は約280万haにも及び、それらの農地は宅地等に転用され、もう元の農地に戻すことはできず、2040年には農地はさらに約2割程度減少すると推計されている(注22)。この問題は、現在農水省が進める農地の集積や集約化で解決できる問題ではなく、そもそも農地のパイが不足する可能性を示唆するものであり、より致命的な問題である。
第3に、労働力の不足である。1960年には1,175万人であった日本の基幹的農業従事者数は(注23)、2000年には約240万人(注24)、2019年には約140万人(注25)にとなり、この20年だけ見ても4割以上も減少している。日本農業研究所では、2040年にはさらに約35万人にまで減少すると推計しており(注23)、平均年齢67歳(注26)と言われる農業現場では今後も労働力不足の致命的な深刻化が懸念されている(図表3)。人口減少社会において、そもそも食べ物の消費量も減少するとの見方もあるが、2040年における国内の推計人口は1億1,092億人で(注27)、その減少率は2019年比でせいぜい-12%程度に留まる。生産年齢人口の減少により、社会全体で労働力不足が叫ばれるが、農業現場の労働者不足はまさに桁違いと言っても過言ではない。加えて、化学肥料や農薬、石油等の輸入資材が途絶える有事においては、現在の機械化・効率化された農業に比べてはるかに多くの労働力を要することも強調しておきたい。

注11.農林水産省「食料自給力指標の手引き」,p.3,(2021.8.18閲覧)
注12.日本経済新聞「農業にもBCPが必要だ 山田敏之氏」,(2020.7.9)
注13.農林水産省「肥料及び肥料原料をめぐる事情」,(2021.8.18閲覧)
注14.農林水産省「有機農業をめぐる我が国の現状について」,p.12,(2021.8.18閲覧)
注15.北海道農政部「有機導入の手引き(小麦編)」,p.15,(2021.8.18閲覧)
注16.北海道中央農業試験場「有機農業の技術的課題と試験研究」,p.1,(2021.8.18閲覧)
注17.北海道立総合研究機構「ばれいしょの疫病による塊茎腐敗の発生生態と防除について」,p.1,(2021.8.18閲覧)
注18.農林水産省「有機農業をめぐる事情」,(2021.8.18閲覧)
注19.松下幸之助(1976)「新国土創成論」PHP研究所,p.19
注20.農林水産省「荒廃農地の現状と対策について」,(2021.8.18閲覧)
注21.農林水産省「令和2年度耕地面積(7月15日現在)」,(2021.8.18閲覧)
注22.農林水産省「食料・農業・農村政策審議会企画部会(令和2年1月29日),配布資料1,p.1,(2021.8.18閲覧)
注23.日本農業研究所「農家人口、農業労働力のコーホート分析」,大賀治,2015,p.98,(2021.8.18閲覧)
注24.農林水産省「農林業センサス」,第2巻 農家調査報告書(総括編),2000年,表番号21,(2021.8.18閲覧)
注25.農林水産省「農業構造動態調査」,調査結果の概要,2019年, p.6,(2021.8.18閲覧)
注26.農林水産省「農業構造動態調査」,確報,2019年,表番号2-1-2-オ,(2021.8.18閲覧)
注27.総務省「2040年頃までの全国人口見通しと近年の地域間人口移動傾向」,(2021.8.18閲覧)
3.農政ビジョン2040
(1)農業が持つ2面性
農業には、2面性があると考える(図表4)。第1に、経済活動としての一面である。農家が農産物を生産して販売し、生活に必要な収入を得る。これは、他の産業と同様の一面である。第2に、国民の食料生産を担う一面である。農業は、国民生活の基盤となる食料の生産を担っており、採算性がないからといって生産をやめるわけにはいかないのである。世界各国において、農業が補助金で保護される所以であろう。しかし、両者はそもそも目的が異なり、目指すべき目標値(KPI)も異なる。食料生産を担う一面からすると、食料自給率や食料自給力指標は重要なKPIであるが、経済活動の一面からすると農業所得や輸出額が重要なKPIであり、個々の農家にとって食料自給率は高くても低くても特に関係ないのである。この農業の2面性を一緒くたに捉えてしまうことこそが、問題の構造を複雑化させ、農業政策の迷走を招いているのではなかろうか。北海道の大規模農業と、中山間地域の小規模農業を、1つの統一的な政策で括ることもあまりに不合理である。
「攻めの農業」の観点から見れば、小規模な兼業農家への助成はやめて、担い手に農地を集積するべきとの考え方になるであろう。しかし、中山間地域のような条件不利地は攻めの農業には適さず、耕作放棄地となることも多い。一方で、農地が絶対的に不足する我が国にとっては、中山間地域も貴重な農地であるため、有事に備えて耕作を継続し、農地を維持しなければならないのである。有事を想定すると、例えば北海道に生産を集中させるより、小規模であっても全国各地に農地が点在している方が物流の観点からもリスク分散の観点からも有効性が高いのである。よって、今回は「守りの農業」に主眼を置き、「農業は採算が合わない場合にも、食料生産を維持するために国費を投じてでも耕作を継続しなければならない」ことを基本方針として議論を進めて参りたい。

(2)あるべき姿
有事に備えて、平時から食料自給率を上げる努力をすることは言うまでもなく重要である。しかし、目標値とするのは、平時の食料自給率ではなく、やはり有事の食料自給力指標であり、有事の際にどれだけ国民の胃袋を満たすことができるかが重要である。そのため、食料自給力指標を100%にすることを目標とするべきである。そして、その食料自給力指標は、輸入に依存する化学肥料や農薬を用いない場合でも100%を達成することを目標とする(図表5)。そのために必要な具体的政策について、次項で詳しく述べたい。
尚、今回はあえて詳述しないが、食料や生産資材が輸入できないような緊急事態においては、当然石油等のエネルギー資源の確保も期待できないことが予測される。これは農業に限ったことではないが、有事においても国民生活を維持することができるように、再生可能エネルギーを推進してエネルギー自給率を高めることが大前提である。そうでなければ、物流の停止によってせっかく生産した食料も国民の手元に行き渡らせることができない。農業機械においては、今年1月にクボタが電動トラクターの商用化を発表したが(注28)、こうした輸入エネルギー資源に依存しない農業機械の普及も不可欠であろう。また、種子についても同様である。例えば、野菜の自給率は79%(2019年度)であるが(注29)、国内で出回る野菜の種子の約9割が海外で採種されていることを考慮すると(注30)、実質的な自給率は8%を下回ることとなる。エネルギーや種子を国内で自給することなくして、真の食料自給国家の実現には至らないのが現実であるが、これらの問題については別稿に譲ることと致したい。

注28.日本経済新聞「クボタ、電動トラクター商用化 3年後めど」,(2020.01.15)
注29.農林水産省「食料自給率の推移」,(2021.8.18閲覧)
注30.日本農業新聞「コロナ禍で社員派遣できず 海外生産が9割 品質管理やきもき 種苗メーカー」,(2020.7.21)
(3)食料自給国家の実現に向けた3つの基本方針
食料自給国家の実現に向けて、3つの基本方針を掲げたい。
第1に、有機農業の取組面積の拡大である。我が国は、農業生産に要する化学肥料や農薬の大部分を海外からの輸入に頼っており、それらを国内で自給することは難しいことは既に述べた。そうなると、有事の際に備えてこうした輸入資材に依存しない農業への転換を図ることが重要である。すなわち、有機農業の面積割合の拡大と、それによる有機農業の技術やノウハウの蓄積である。農水省は、2021年5月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、2050年までに有機農業の取組面積割合を25%に拡大する目標を定めた(注31)。しかし、この高い目標を実現するための具体策については、あまり触れられていない。次章では、有機農業の取組面積拡大に向けた具体策について提言したい。
第2に、農地の維持と拡大である。既に宅地等に転用されて失われた農地は、もう元に戻すことはできない。しかし、耕作放棄地の増加に歯止めをかけて、今ある農地を最大限維持することは可能である。さらに、再生可能な荒廃農地については、最大限再生に取り組むべきであろう。そのための具体策については、次章で2つ提言したい。
第3に、労働力不足への対応である。その方向性として、①スマート農業の普及推進、②外国人労働力の拡大、③潜在的な国内労働力の農業への誘引を掲げる。これらを進めるための具体策については、次章で提言する。
注31.農林水産省「みどりの食料システム戦略の策定について」,(2021.8.18閲覧)
4.7つの提言
(1)【提言①】有機農産物の学校給食導入
我が国の有機農業の面積割合は、0.5%に留まり、EU諸国の7%と比べても著しく低い(注32)。農地面積が小さい我が国にとっては、面積当たりの収量を上げることが重要であり、肥料や農薬を用いることは有効である。有機農業の拡大は、むしろ食料自給率を下げることにも繋がりかねない。しかし、肥料や農薬が輸入できないような有事を想定すると、平時から有機農業の取組面積を一定割合まで高めてプレーヤーを増やし、有機農業に関する技術や知見を集積することも極めて重要である。
例えば、北海道更別村・幕別町のバイオダイナミックファーム「トカプチ株式会社」では、360haにもおよぶ大規模有機農業に取り組んでおり、将来的に1,000haの有機農場を構想している(注33)。有機農業では除草剤を使用できないため、雑草を手作業で取り除く。このため、膨大な人手と時間を要し、有機農業の大規模経営は難しいというのが一般的な認識だ。しかし、トカプチでは小麦の播種時に白クローバーを混播することで白クローバーが表土を覆い、他の雑草の繁茂を抑制することに成功している(注34)。白クローバーは草丈が低いため、小麦の生育や収穫作業を阻害しない。これにより、除草剤を使用することなく、かつ人手も要することなく、有機農業の大規模経営を実現している。こうした知恵やノウハウは、やはり有機農業に取り組むプレーヤーが一定数いなければ蓄積されないであろう。慣行農業と有機農業のどちらが良いかという議論ではなく、両者の適正なバランスが重要なのである。
有機農業の拡大に向けた具体策として、有機農産物の学校給食への導入を提言したい。千葉県いすみ市では、2014年に民間から指導者を招いて有機農業への取り組みを本格化し、必要な設備投資について市が助成を行っている(注35)。そして、2017年には市内の小中学校の学校給食で使用するお米全量を市内で生産された有機米に切替えた(注36)。安定した売り先が確保されたことで、農家も積極的に有機農業に挑戦することができるとともに、子ども達が有機農産物を口にする機会が増えることは、食育の観点からも有機農産物への関心の喚起に繋がる。有機農業を拡大するためには、まず消費者の意識を高め、需要を創出することが重要と考える。
注32.独立行政法人農畜産業振興機構「EUにおける有機(オーガニック)農業の現状,(2021.8.18閲覧)
注33.アグリシステム株式会社「バイオダイナミックファームトカプチ株式会社」,(2021.8.18閲覧)
注34.アグリシステム株式会社「大規模有機栽培の展望と可能性」,(2021.8.18閲覧)
注35.鮫田晋,千葉県いすみ市農林課,オンライン,(2021.7.14インタビュー)
注36.千葉日報「給食、全て有機米に 全国初、いすみ市が実現」,(2017.10.27)
(2)【提言②】企業による農地取得の段階的な規制緩和
農業者の高齢化と後継者不足により、手放される農地は今後いっそう増加する。新たな農業の担い手として、企業の農業参入を促進するため、企業による農地取得を認めていくことは重要だ。しかし、何でもかんでも全面的に認めるのが良いわけではない。そこで、企業による農地取得の段階的な規制緩和を提言する。
所有権の移転ではなく、リース方式によって企業が農地を貸借し、農業に参入することは現行の農地法でも認められている(注37)。このことから、「企業による農地の所有を認めなくても、現行のリース方式で十分ではないか」との農業者の声もある(注38)。たしかに、国家戦略特区での規制緩和によって企業の農業参入が増えたと総括する兵庫県養父市の実績を見ても、新規参入した法人件数はリースと所有を合わせて13件、農地面積は61.41haであるのに対し、そのうち農地取得の特例を活用(リースではなく所有)した法人の件数は6件、農地面積は1.66haに留まる(図表、注39、注40)。このことを踏まえても、企業の農業参入が増えた要因として「農地の所有を認めること」が決定打であったとは必ずしも言い切れない状況だ(図表6)。
一方で、筆者が行った農業者の方々との意見交換では「作物を屋外の畑や水田で栽培する露地栽培においては現行のリース方式で十分かもしれないが、高額な投資を要するビニルハウス等の施設園芸や植物工場を借地に立てることは現実的ではなく、農地の所有を認めても良いのではないか。また、露地栽培であっても、土壌改良に数年を要する有機栽培の場合や、発芽・定植から生産物を生むに至るまで数年を要する果樹や茶などの永年作物については、リース方式では難しいのではないか。」との意見があった(注38)。たしかに、高額な設備投資を要する作物や、投資の回収に数年を要する作物を期限付きの借地上で栽培することは、企業にとってあまりにもリスクが大きすぎる。実際に、養父市での事例においても、植物工場の建設に多額の設備投資をした法人からは「農地を借りて万が一にでも返却して欲しいと言われたらどうしようもなくなってしまう。自社所有した方が安心できるので購入することにした。」との声が上がっている(注41)。
以上のことから、まずは施設園芸や植物工場、有機栽培、永年作物に限定して、企業による農地取得を認めることを提言したい。この他、「外国資本に農地が買い占められるのではないか」、「地域の共同作業に参加しないのではないか」という懸念の声も多く見られた(注38)。企業による農地取得を段階的に認めていく上では、こうした懸念に対する対応が不可欠であろう(図表7)。


注37.農林水産省「企業等の農業参入について」, (2021.8.18閲覧)
注38. 農業者,SNS, (2021.1.21聞き取り)
注39. 養父市「養父市が活用している規制改革メニュー・特区事業者の紹介」, (2021.8.18閲覧)
注40. 養父市企画総務部国家戦略特区・地方創生課,電話・メール, (2021.5.6聞き取り)
注41. 養父市「特区対談#06 中山間農業の存続に向けて 養父市における企業農業の取組」, (2021.8.18閲覧)
(3)【提言③】農地の指定管理
肥沃で条件の良い農地は、地元の担い手農家や農業法人が経営を継承することが期待される。一方で、中山間地域等の条件の良くない農地は資本主義的な経営判断では採算が合わず、耕作放棄地となってしまう可能性が高い。しかし、我が国は貴重な農地を維持しなければならないのであり、そのためには公営で農業経営を継承するような社会主義的な政策が必要であろう。
北海道深川市では、2017年に深川市と地元のJAきたそらちの共同出資で(株)深川未来ファームを設立した(注42)。同社の経営収支は、農産物の販売では採算が取れていないのが現状であるが、地元の農地の保全や新規就農者向けの研修等といった公的な役割も大きいことから、公費を投じて自治体が農業経営に取り組む先駆的な事例である。
また、公民館等の公の施設の管理・運営をノウハウのある民間事業者に委ねる指定管理者制度が広がりを見せているが(注43)、農地についても指定管理の導入を提言したい。すなわち、引き受け手のいない耕作放棄地を自治体が買い取り、その管理・運営をノウハウのある地元の農業法人やJAに委ねるということである。これにより、条件の良くない農地においても、耕作を維持し、経営赤字を最小限に抑えることができるであろう。農地の維持は食料安全保障のための国策であり、国による財政的な支援も不可欠である。
注42.株式会社深川未来ファーム「会社概要」,(2021.8.18閲覧)
注43.総務省「公の施設の指定管理者制度について」,(2021.8.18閲覧)
(4)【提言④】国が賠償責任を負う先端技術の規制緩和
労働力不足を補うために、最先端のロボット技術やICTを活用したスマート農業の普及推進は不可欠だ。北海道大学の野口伸教授は、「無人でトラクターを運転する技術は日本が先駆けて実用化できた」と指摘しており(注44)、スマート農業で世界をリードする立場が明確になってきている(注45)。しかし、優れた先端技術を持ちながら、その普及が進まない大きな要因の1つが、こうした新技術に対する法整備が追い付いていないことだ。
普及の障壁となる規制の代表例として、農業機械の自動走行に関する規制が挙げられる(図表8)。農水省が示す「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」によれば、ロボットトラクターの公道(農道)での自動走行は原則禁止とされている(注46)。しかし、公道走行ができなければ農機具庫から圃場までの移動および圃場間の移動においては人が乗って運転することが必要となり、省力化の効果を十分に得ることができない。また、ほ場内においても自動走行時には使用者の監視が義務付けられており、これでは結局人手が必要となってしまう。最終目標である遠隔地からの指示・監視による完全自動での運用に向けては、道路交通法の改正等さらに大胆な規制緩和が不可欠である。
もう一つの規制の代表例として、農薬散布ドローンに関する規制が挙げられる(図表9)。農薬散布ドローンについても予め設定したルートに基づいて誤差数センチの精度で離陸から着陸まで完全自動飛行する技術が既に確立されている。しかし、航空法に基づき国土交通省が策定した「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」では、操縦者の他に原則もう一名補助者による監視が義務付けられている(注47)。すなわち、本来は自動でできる作業について、2名の人員を要することとなり、省力化どころかかえって余計に人手を要するような規制の現状となっているのである。さらに、農水省が示す「空中散布等における無人航空機利用技術指導指針」では、ドローンの機体とオペレーターの距離は、水平距離で150mを超えない範囲とされているが(注48)、北海道のような広大な圃場では150m以上離れずには全く使い物にならないとの現場の声もある。
自動運転や自動飛行の規制緩和をめぐる議論で難航するのが、万一の事故の時に誰が責任を取るかという点だ。すなわち、使用者である農業者と、製造者であるメーカーとの間で責任の所在が不明確となっているのである。むろん、一定程度の安全性が確認されていることは大前提であるが、出始めの技術である以上、誰かがリスクを引き受けて責任を負わない限り、新技術の普及は進まないように思う。そこで、出始めの段階にある新技術については、国が賠償責任を負うことで規制緩和と普及促進に取り組んではどうか。新型コロナウィルスに対するワクチンの実用化においても、迅速な接種拡大を図るために、健康被害の賠償責任を国が肩代わりすることで実用化が大幅に早まった(注49)。農業現場の深刻な労働力不足も、もはや待ったなしの状況であり、優れたスマート農業技術の一刻も早い普及には迅速な規制緩和が不可欠なのである。


注44.日本経済新聞「NTTグループ 北大などと農業ロボットで連携協定」,(2019.6.28)
注45.AGRI JOURNAL「『無人での完全自律走行』が実現化!?2020年、スマート農機は大きく進化する」,(2019.8.15)
注46.農林水産省「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」,(2021.8.18閲覧)
注47.国土交通省航空局「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」,(2021.8.18閲覧)
注48.農林水産省消費・安全局「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」,(2021.8.18閲覧)
注49.日本経済新聞「コロナワクチンの賠償、国が責任」,(2020.8.20)
(5)【提言⑤】農村における日本語学校の設立
近年、技能実習や特定技能の在留資格で就労する外国人が日本の農業生産を支える大きな力となっている。厚生労働省の外国人雇用状況の届出状況によると、2009年には「266人に1人」であった農業・林業で働く外国人労働者の割合は、2017年には「74人に1人」と急増しており、特に農業の外国人依存度が最も高い茨城県では、「21人に1人」が外国人で、20代に限ると約2人に1人が外国人となっている(注50)。日本の農業現場で就労する外国人の数は、今後も一層の増加が見込まれる。
農業現場の労働力不足を外国人労働力で補うことは、今後より一層重要であろう。しかし、コロナ禍で来日予定であった技能実習生が入国できなくなったことにより、外国人に依存していた農業現場では大きな混乱が生じている(注51)。長期的な食料安全保障を考える上では、労働力の自給率も重要であることがわかる。現在、技能実習や特定技能1号の在留資格による在留期間は最長5年までとなっており、家族の帯同や永住申請が可能な特定技能2号では農業は対象外となっている(注52、注53)。しかし、日本の食料生産を担う安定した労働力として定着を図るには、農業に従事する外国人労働力に永住を認めることが長期的には不可欠ではなかろうか。
「外国人労働者が増加すると日本人の雇用が奪われる」との批判があるが(注54)、それは誤解だ。現状でも、農業現場では慢性的な労働力不足が続いている。だが、首都圏や都市部で求職する労働者が農村に移住して就職することはほとんどない。すなわち、日本人の求職者と農村の求人にはミスマッチが生じているのであって、農業に従事する外国人が増えるからと言って日本人の雇用が奪われることはないと言える。
また、町に暮らす外国人が増えることで、治安の悪化や、文化・習慣の違いによる生活マナーの問題が懸念されることも多くある。実際に、住民約5,000人のうちの半分以上を外国人が占める埼玉県川口市の芝園団地では、「ごみの分別が出来ておらず、ごみ捨て場にごみが散乱する」、「夜遅くに広場で騒ぐのがうるさい。玄関のドアを開けっぱなしで騒いでいる」等の生活トラブルが目立っている(注55)。
一方で、外国人が多く暮らす農村である北海道東川町では、2015年に開校した国内初の「公立」の日本語学校の取り組みによって農村における外国人との共生に成功している。東川日本語学校では、「単に日本語を教えるだけでなく、日本の生活習慣を学ぶ機会や、茶道体験等を通じた日本人の心を学ぶ機会を設けており、日本人の住民とのトラブルや苦情はあまり聞かない(注56)」とのことで、同校の奥山富雄校長は、「留学生には小中学校の国際交流教科の時間や、地域の盆踊り・敬老会などにも積極的に参加してもらい、町民との交流も深めている(注56)」と語る。トラブルが増えるからと言って外国人の受入れに否定的になるのではなく、トラブルを減らすために何ができるかを考えることが農村における多文化共生の実現に向けて重要な姿勢ではなかろうか。そこで、農村に公立の日本語学校を開校し、日本語だけでなく、日本の生活習慣や日本人の心を学ぶ機会を設けることで、農村における外国人との多文化共生地域づくりを進めることを提言したい。
注50.日本経済新聞「農業の外国人依存度、1位は茨城県 20代は半数」,(2018.08.09)注51.朝日新聞デジタル「コロナ禍で技能実習生来日できず 野菜生産に影響」,(2021.5.7)
注52.公益財団法人国際人材協力機構「外国人技能実習制度とは」,(2021.8.18閲覧)
注53.公益財団法人国際人材協力機構「在留資格『特定技能』とは」,(2021.8.18閲覧)
注54.日経ビジネスオンライン「『外国人に仕事を奪われる』は本当か」,(2018.11.9)
注55.PHP総研「『隣近所の多文化共生』の課題―芝園団地の実態と実践から―」,岡崎広樹,p.2,p.4,(2021.8.18閲覧)
注56.奥山富雄,東川町立東川日本語学校校長,東川町立東川日本語学校,(2021.6.28インタビュー)
(6)【提言⑥】潜在的な国内労働力の誘引
外国人労働力を頼ることも必要であるが、国内においても農業現場で活躍が期待される潜在的な労働力が多く眠っている。それは、国内に100万人以上いると推計されるひきこもり状態にある人や(注57)、退職後のアクティブシニアである。
内閣府の生活状況に関する調査によると、15~39歳で541,000人、40~64歳で613,000人がひきこもり状態にあるとされている(注57)。2040年までに基幹的農業従事者が約105万人減少すると予測される中、100万人以上の潜在的な生産年齢人口を農業に誘引することができれば、農業現場の労働力不足は大きく軽減されることが期待される。
北海道安平町の農業生産法人(株)耕せにっぽんでは、ひきこもり状態にある若者を親元から大自然に連れ出し、全寮制の共同生活と農業研修を通じた自立支援に取り組んでいる(注58)。約1年間の研修を経て、これまで約400名の若者が就労と自立を果たしており、その中には就農した人もいると言う(注59)。この事例から、引きこもり状態にある人々が農業現場で力を発揮する大いなる可能性を感じずにはいられない。何より、こうした取り組みは、自信や希望を持てずに思い悩む引きこもりの若者達にとっても、人生に希望の光を取り戻す大きな契機となるものであろう。
また、退職後のアクティブシニアにも農業の担い手となりうることが期待される。生産年齢人口は、15歳以上65歳未満の人口と定義されるが、近年は65歳を超えても、活発で元気なシニアの方が本当に多いように思う。(一財)日本総合研究所の寺島実郎会長は、シニア世代にとって重要な社会参画の分野として、まず最初に挙げておきたいのが「食と農」であると指摘している(注60)。横浜市に住むシニア仲間で構成される浜っ子中宿農園では、長野県飯綱町でりんごやプルーン、さくらんぼ等の果樹を栽培しており、約30人の会員が横浜と飯綱町を行き来することで成り立っている(注61)。定年退職後に住み慣れた住居を手放し、農村に移り住むとなると心理的負担が大きい人も多いかもしれない。だが、都市部での生活基盤を維持しながら、年間の栽培スケジュールに応じて月に数日から数週間ほど通いで農業に携わるこの様式であれば、都市部のシニア世代にも取り組みやすいのではなかろうか。経理に詳しい人は経理、営業が得意な人は営業を担当する等、会社員時代の経験や強みを生かして各人が力を発揮できる点も特徴的だ。何より、こうした取り組みはシニアにとっても生きがいや役割の創出といった利点が多く、健康寿命の延伸や介護予防にも繋がるものと思う。
このように、国内の潜在的な労働力を農業に誘引することで、労働力不足を補うことも重要であろう。
注57.日本経済新聞「中高年ひきこもり61万人 内閣府が初調査」,(2019.3.29)
注58.農業生産法人株式会社耕せにっぽん「耕せにっぽんとは」,(2021.8.18閲覧)
注59.東野昭彦,農業生産法人株式会社耕せにっぽん代表取締役社長,農業生産法人株式会社耕せにっぽん本社,(2021.8.13インタビュー)
注60.寺島実郎(2018)「ジェロントロジー宣言」NHK出版新書,p.153注61.寺島実郎(2018)「ジェロントロジー宣言」NHK出版新書,p.160
(7)【提言⑦】予備農家の養成
スマート農業や外国人労働力、国内潜在労働力のフル活用によって労働力不足を補う必要があることは既に述べた。しかし、有事においては、更に多くの労働力を農業生産に要することが予想される。食料が輸入できないような緊急事態においては、化学肥料や農薬、農業機械や貨物自動車の動力となる原油も輸入できない事態である可能性が高く、全ての農作業を人の手で行う必要があるためである。有事への備えという点においては、自衛隊には普段は自衛官ではない人々が事前に訓練を行って有事の緊急招集に備える「予備自衛官等制度」がある(注62)。そこで、これと同様に、食料安全保障においても有事に備えた「予備農家」を養成することを提言したい。むろん、農業に従事するにあたっては、自衛官のような長期間かつ厳格な訓練は必ずしも要しない。だが、田植えや稲刈りをやったことがない人ばかりでは、いざという時に国民の総力を結集して食料生産に取り組むとなっても、その力を有効に発揮することは難しいように思う。予備農家を養成する具体的手法は、義務教育における農業体験の延長線上のレベルでも構わない。重要なことは、単なる体験として終えるのではなく、いざとなれば自分がこの作業に従事して自分が食べる食料を自分で生産するのだという現実的な自覚を持つことである。そして、訓練の段階から各人が担当する地域や作物を明確にしておくことで、緊急時の食料生産はより効率的に行えるのではなかろうか。
注62.政府広報オンライン「有事の際、国を支える力になる!『予備自衛官等制度』」,(2021.8.18閲覧)
5.結び
この国にとって、今一番大切なことは何であろうか。経済対策、教育、医療福祉の拡充等、どれも非常に重要な課題である。しかし、それらはどれも「国民の命」があってこそのものであり、そしてその命は「十分な食料」があってこそのものだ。有事の食料安全保障は、国民生活の根幹を支える最も重要な課題であると私は考える。
2040年の農業の展望は、今私たちが想像している以上に非常に厳しい。加えて、国際情勢は今以上に緊張感を増し、各国が保護主義に向かい、世界人口は爆発的増加を続ける。これまで起こらなかった事態が起こり、これまで当たり前のように輸入できた食料や農業資材が輸入できなくなる事態が、現実に起こりうる時代になるであろう。
今回のコロナ禍で、マスクが突然店頭から姿を消した。製造の大半を中国に依存するマスクの国内自給率は、約23%であった(注63)。普段、「当たり前」のようにあるもののありがたみは、失った時に初めて気付く。そして、多くの場合、気付いた時にはもう既に手遅れである。「当たり前」のようにある食べ物のありがたみを、私たち日本人はどこか忘れかけてはいないだろうか。
今こそ、その「当たり前」の重要性を再認識し、我が国も食料自給国家の実現に向けて真剣に取り組むべき時である。
注63.一般社団法人 日本衛生材料工業連合会「マスクの統計データ」,(2021.8.18閲覧)
<参考文献>
[1] 農業協同組合新聞「過去最低の自給率 大きい目標との乖離」
https://www.jacom.or.jp/nousei/closeup/2019/190807-38855.php (2019.8.7)
[2] 農林水産省「日本の食料自給率」
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012.html (2021.8.18閲覧)
[3] SankeiBiz「温暖化で穀物価格23%上昇 国連IPCC、2050年見通し警告
https://www.sankeibiz.jp/macro/news/190812/mca1908120500004-n1.htm (2019.8.12)
[4] 国際連合広報センター「世界人口推計2019年版」
https://www.unic.or.jp/news_press/features_backgrounders/33798/ (2021.8.18閲覧)
[5] ジュリアン・クリブ(2011)「90億人の食糧問題」シーエムシー出版
[6] 農林水産省「平成22年度 食料・農業・農村白書 全文」,2010,巻末付録,p405
https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/h22/zenbun.html (2021.8.18閲覧)
[7] 菅正治(2020)「平成農政の真実 キーマンが語る」筑波書房
[8] 農林水産省「日本の食料自給力」
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/012_1.html (2021.8.18閲覧)
[9] 農林水産省「緊急事態食料安全保障指針」
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/shishin.html (2021.8.18閲覧)
[10] 農林水産省「食料自給力指標の手引き」
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/012_1-11.pdf (2021.8.18閲覧)
[11] 日本経済新聞「農業にもBCPが必要だ 山田敏之氏」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61284150Y0A700C2SHE000/(2020.7.9)
[12] 農林水産省「肥料及び肥料原料をめぐる事情」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/senryaku_kaigi/pdf/01_siryo3.pdf (2021.8.18閲覧)
[13] 農林水産省「有機農業をめぐる我が国の現状について」
https://www.maff.go.jp/primaff/koho/seminar/2019/attach/pdf/190726_01.pdf(2021.8.18閲覧)
[14] 北海道農政部「有機導入の手引き(小麦編)」
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/yukitebiki_komugi.pdf (2021.8.18閲覧)
[15] 北海道中央農業試験場「有機農業の技術的課題と試験研究」
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/shingijutsu/22/pdf/17.pdf (2021.8.18閲覧)
[16] 北海道立総合研究機構「ばれいしょの疫病による塊茎腐敗の発生生態と防除について」
https://www.nippon-soda.co.jp/nougyo/pdf/no198/198_001.pdf (2021.8.18閲覧)
[17] 農林水産省「有機農業をめぐる事情」
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/attach/pdf/meguji-full.pdf (2021.8.18閲覧)
[18] 松下幸之助(1976)「新国土創成論」PHP研究所
[19] 農林水産省「荒廃農地の現状と対策について」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/special/2030tf/281114/shiryou1_2.pdf (2021.8.18閲覧)
[20] 農林水産省「令和2年度耕地面積(7月15日現在)」
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kekka_gaiyou/sakumotu/menseki/r2/kouti/index.html (2021.8.18閲覧)
[21] 農林水産省「食料・農業・農村政策審議会企画部会(令和2.1.29),配布資料
https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/kikaku_0129.html (2021.8.18閲覧)
[22] 日本農業研究所 大賀圭治「農業人口、農業労働力のコーホート分析
http://www.nohken.or.jp/28-2ooga063-102.pdf (2021.8.18閲覧)
[23] 農林水産省「2000年世界農林業センサス報告書」
https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2000/houkokusyo.html (2021.8.18閲覧)
[24] 農林水産省「平成31年農業構造動態調査」
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukou/ (2021.8.18閲覧)
[25] 総務省「2040年頃までの全国人口見通しと近年の地域間人口移動傾向」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000573853.pdf (2020.1.25閲覧)
[26] 日本経済新聞「クボタ、電動トラクター商用化 3年後めど」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO54410960V10C20A1000000/ (2020.01.15)
[27] 農林水産省「食料自給率の推移」
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/zikyu_ritu/attach/pdf/012-15.pdf (2021.8.18閲覧)
[28] 日本農業新聞「コロナ禍で社員派遣できず 海外生産が9割 品質管理やきもき 種苗メーカ」
https://www.agrinews.co.jp/p51410.html (2020.7.21)
[29] 農林水産省「みどりの食料システム戦略の策定について」
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/kankyo/210512.html (2021.8.18閲覧)
[30] 独立行政法人農畜産業振興機構「EUにおける有機(オーガニック)農業の現状
https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_000833.html (2021.8.18閲覧)
[31] アグリシステム株式会社「バイオダイナミックファームトカプチ株式会社」
http://www.agrisystem.co.jp/sites/company/tokapuchi.html(2021.8.18閲覧)
[32] アグリシステム株式会社「大規模有機栽培の展望と可能性」
http://www.agrisystem.co.jp/agrisystem_news/2014/01/45.html (2021.8.18閲覧)
[33] 鮫田晋,千葉県いすみ市農林課,オンライン,(2021.7.14インタビュー)
[34] 千葉日報「給食、全て有機米に 全国初、いすみ市が実現」
https://www.chibanippo.co.jp/news/local/449327 (2017.10.27)
[35] 農林水産省「企業等の農業参入について」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/sannyu/kigyou_sannyu.html (2021.8.18閲覧)
[36] 養父市「国家戦略特区と地方創生 養父市の挑戦」
https://www.city.yabu.hyogo.jp/material/files/group/5/tokku.pdf (2021.8.18閲覧)
[37] 養父市「養父市が活用している規制改革メニュー・特区事業者の紹介」
https://www.city.yabu.hyogo.jp/jigyosha/koyo_shugyo/senryakutokku/katuyou/index.html (2021.8.18閲覧)
[38] 養父市「特区対談#06 中山間農業の存続に向けて 養父市における企業農業の取組」
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/taidan06.html (2021.8.18閲覧)
[39] 株式会社深川未来ファーム「会社概要」
https://fukagawamirai-farm.co.jp/company/overview/ (2021.8.18閲覧)
[40] 総務省「公の施設の指定管理者制度について」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000451041.pdf (2021.8.18閲覧)
[41] 日本経済新聞「NTTグループ 北大などと農業ロボットで連携協定」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46715940Y9A620C1X12000/ (2019.6.28)
[42] AGRI JOURNAL「『無人での完全自律走行』が実現化!?2020年、スマート農機は大きく進化する」
https://agrijournal.jp/renewableenergy/46556/ (2019.8.15)
[43] 農林水産省「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」
https://www.maff.go.jp/j/press/seisan/gizyutu/attach/pdf/210326-3.pdf (2021.8.18閲覧)
[44] 国土交通省航空局「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」
https://www.mlit.go.jp/common/001254115.pdf (2021.8.18閲覧)
[45] 農林水産省消費・安全局「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」
http://mujin-heri.jp/hourei/shidoushishin_300331.pdf (2021.8.18閲覧)
[46] 日本経済新聞「コロナワクチンの賠償、国が責任」
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62820190Z10C20A8MM8000/?unlock=1 (2020.8.20)
[47] 日本経済新聞「農業の外国人依存度、1位は茨城県 20代は半数」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO33984730Z00C18A8000000/ (2018.08.09)
[48] 朝日新聞デジタル「コロナ禍で技能実習生来日できず 野菜生産に影響」
https://www.asahi.com/articles/ASP566TG4P4ZUHNB009.html (2021.5.7)
[49] 公益財団法人国際人材協力機構「外国人技能実習制度とは」
https://www.jitco.or.jp/ja/regulation/ (2021.8.18閲覧)
[50] 公益財団法人国際人材協力機構「在留資格『特定技能』とは」
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/ (2021.8.18閲覧)
[51] 日経ビジネスオンライン「『外国人に仕事を奪われる』は本当か」
https://business.nikkei.com/atcl/report/16/021900010/110800080/(2018.11.9)
[52] PHP総研「『隣近所の多文化共生』の課題 芝園団地の実態と実践から」,岡崎広樹
https://thinktank.php.co.jp/wp-content/uploads/2021/03/policy_v15_n80.pdf (2021.8.18閲覧)
[53] 奥山富雄,東川日本語学校校長,東川日本語学校, (2021.6.28インタビュー)
[54] 日本経済新聞「中高年ひきこもり61万人 内閣府が初調査」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43067040Z20C19A3CR0000/ (2019.3.29)
[55] 農業生産法人株式会社耕せにっぽん「耕せにっぽんとは」
https://www.tagayase.com/ (2021.8.18閲覧)
[56] 寺島実郎(2018)「ジェロントロジー宣言」NHK出版新書
[57] 政府広報オンライン「有事の際、国を支える力になる!『予備自衛官等制度』」
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201405/2.html (2021.8.18閲覧)
[58] 一般社団法人 日本衛生材料工業連合会「マスクの統計データ」
http://www.jhpia.or.jp/data/data7.html (2021.8.18閲覧)
.png?1771716221)





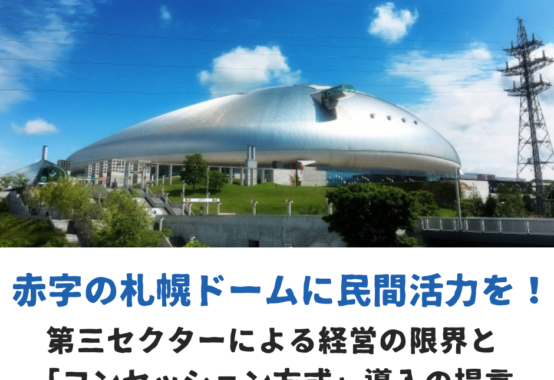






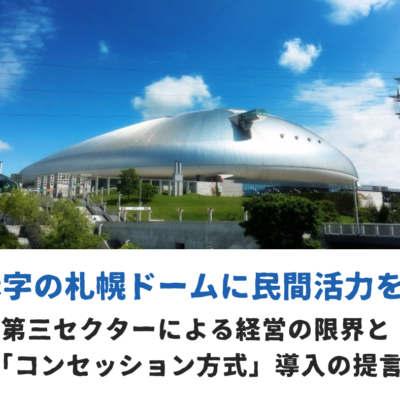







この記事へのコメントはありません。