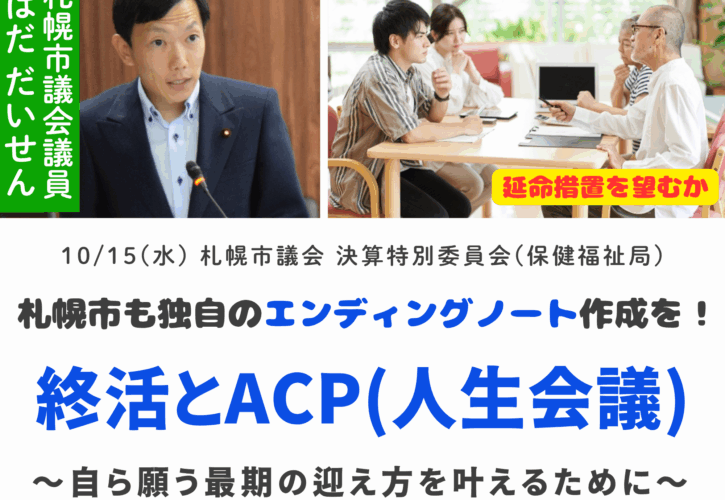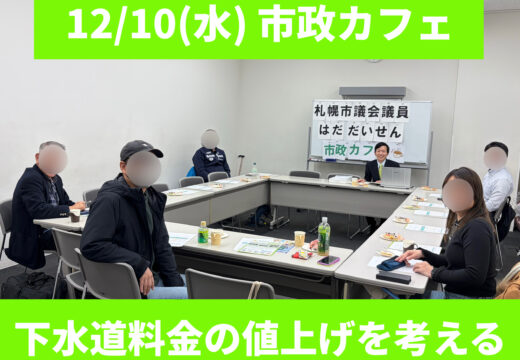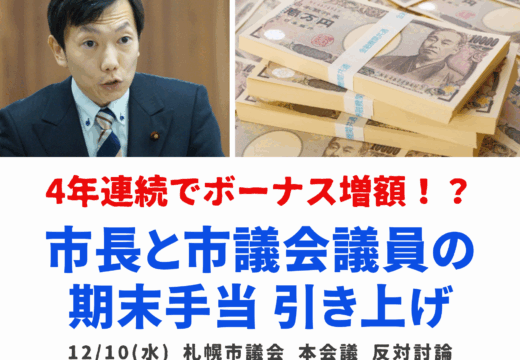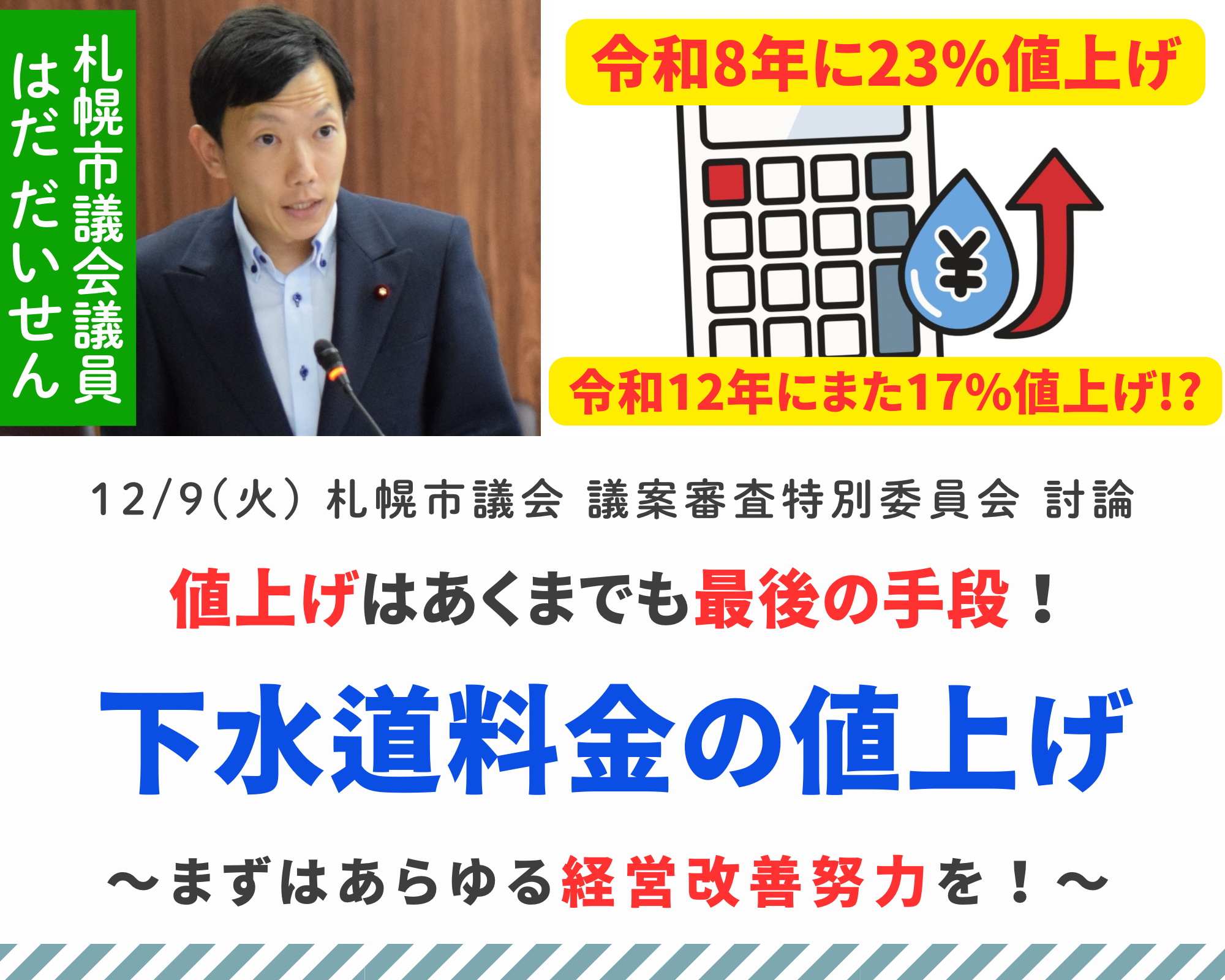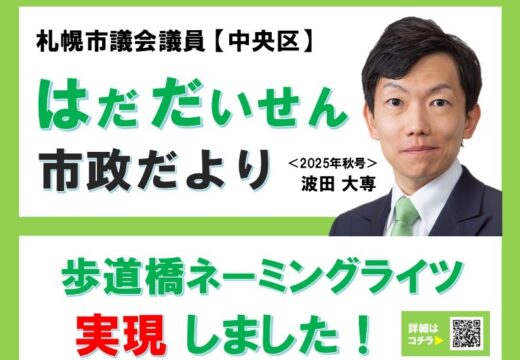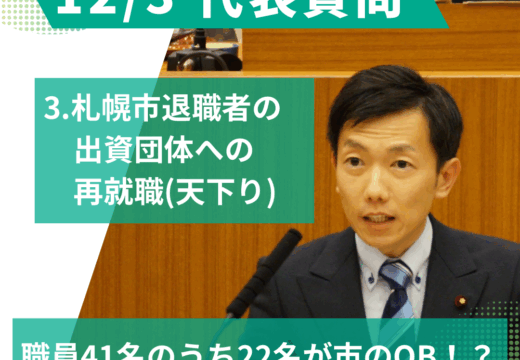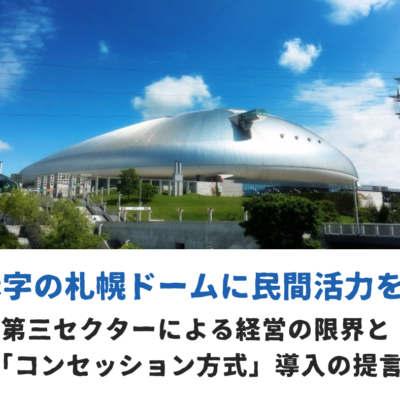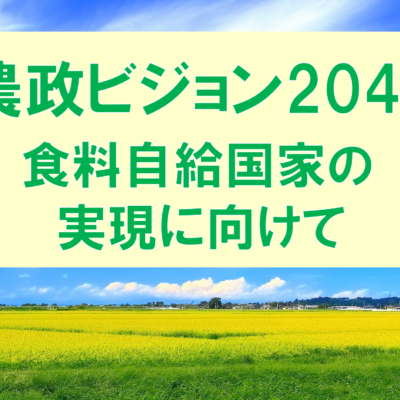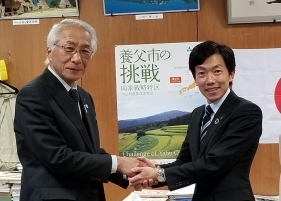10/15(水)、札幌市議会 決算特別委員会(保健福祉局)で「終活」と「ACP(人生会議)」の関わりについて質問しました。
人生の最終段階において、「最期をどこで迎えたいか」「延命措置を望むか」等、自らの望みを前もって考え、共有する「ACP(人生会議)」の認知度は6.5%と低く、「終活」と連携した普及啓発を進めることが重要と考えます。
福岡市では、終活関連事業者からの広告収入を活用した市独自の「エンディングノート」の作成と配布を行っていることから、札幌市でも独自の「エンディングノート」を作成することを提言させて頂きました。
<波田質問>
私からは、「終活」と「ACP」の関わりについて質問させて頂きます。
人生の最終段階において、自らが望む医療やケアについて、前もって考え、家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、共有する取組である「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)=人生会議」について、札幌市でも普及啓発に取り組んでいるとのことでございました。
日々、人生の最終段階と向き合う医療従事者の方によりますと、本人が意思表示できない状況の中で、延命措置を行うかどうか、家族等にその判断が委ねられることとなりますが、どうすれば良いかわからず、何もしてあげないのも可哀想との思いで、延命措置を希望される方も多いそうです。
しかし、細くなった血管に無理に点滴を入れるのは家族としても目を覆いたくなるような状況とのことで、点滴によって体がむくみ、最期は見た目が別人のようになってしまうこともあるようです。本人にも苦痛を伴い、点滴や経管栄養等のチューブを自ら引き抜こうとする手をミトンと言われる手袋で固定するような状況に接する度、一体誰のための延命なのかとの切実なお声もお聞きするところです。
もちろん、延命措置の意義自体を否定するものではありませんが、やはり人生の最期の迎え方は自分自身の選択と意思表示によって決めるべく、お元気なうちに早い段階から「ACP」に取り組み始めることが重要であり、市民への普及啓発が極めて重要であると考えます。
近年では、人生の最期を迎えるにあたって、自身の財産や身の回りの整理、葬儀・お墓の準備、相続に関する計画などを行う「終活」に取り組む方も多く、札幌市でもウェルネス推進部施設管理課で終活セミナーやワークショップなど参加型のイベント開催や、市役所及び各区役所で実施している終活に関連する業務の情報提供を行っており、令和6年度決算では「終活ネットワーク構築推進費」として約180万円が支出されております。
もちろん、「終活」と「ACP」は異なる概念ではありますが、「終活」に関心を持つ市民の方に対して、「ACP」についても併せて情報提供などを行うことで、ACPの認知度向上や具体的な行動変容にも繋がるものと考えます。
そこで、質問ですが、「ACP」の認知度向上を図るため、「終活」に関心を持つ市民の方に対して、「ACP」についても併せて情報提供などを行うべきと考えますが、お考えをお伺い致します。
<答弁の趣旨>
○札幌市では、 終活に取り組む市民を増やしていくことが重要と考えていることから、ワークショップなどを開催し、終活支援を行っているところ。
○ACPは終活で扱う幅広いテーマの1つであることから、今後、 作成を予定している終活ガイドブックにおいてACPについて紹介することや、終活サロンの場において情報提供を行うことなどを検討してまいる。
<波田質問>
ぜひ「終活ガイドブック」や「終活サロン」において、ACPについても連携して普及啓発に取り組んで頂きたいと思います。
「終活」の取り組みの1つとして、「エンディングノート」が活用されており、自分自身に何かあったときに備えて、財産状況や交友関係、葬儀・お墓について等、ご家族が様々な判断や手続を進める際に必要な情報を残すためのツールとなっております。
近年では、「緩和ケアや延命措置を望むか」「病院・施設・自宅、どこで最後を迎えたいか」等、医療や介護に関する希望についても内容に盛り込まれているものも多く、「エンディングノート」は「ACP」の普及啓発においても効果的なツールとなり得るものと考えます。
「エンディングノート」は、市販のものや民間団体が発行しているものに加えて、自治体が独自に作成して配布している例も多く、多くの政令市でもオリジナルのエンディングノートを作成し、配布しています。
一方で、札幌市の「終活に関する情報」を掲載したWEBページによれば、「よくある質問」の項目の中に「札幌市ではエンディングノートを配布していますか?」との質問があり「配布しておりません。書店等でお求めください。」との回答が掲載されております。
しかし、よくある質問ということは、市民の皆さんからの要望の声も多いのではないかと拝察するところです。
「エンディングノート」によって「終活」や「ACP」の普及啓発を促進することは、市民の皆さんが願う最期の迎え方を叶える上でも重要であると考えます。
そこで、質問ですが、札幌市として、独自の「エンディングノート」の作成や配布に取り組むお考えはないか伺います。
<答弁の趣旨>
○終活を行うに当たりエンディングノートを書くことは、身の回りの整理や自分を見つめ直す良い機会になることから、終活ガイドブックにおいて、エンディングノートに書き込む内容についても取り上げることとしている。
○なお、札幌市として独自のエンディングノートを作成することは、現時点では考えていないが、法務局においてひな形を作成していることは承知しており、そのような公的機関の情報をホームページなどで紹介してまいる。
<波田要望>
「エンディングノート」の書き方のポイント等について周知することも重要とは思いますが、やはり札幌市が作成するエンディングノートで、ひな形で定められた項目に沿って記入しながら、ノートの空欄を埋めていく方が、初めての方でも気軽に取り組みやすいものと考えます。
例えば、福岡市では、市独自で「マイエンディングノート」を作成して配布しておりますが、巻末に各種相談・手続き先一覧として関係する庁内部署の電話番号が一覧になっている点が、市販のものとは異なる特徴と感じました。
また、毎年2万部以上を発行しても全て無くなってしまう程のニーズがあるとのことで、予算もかなり投じられているものかと思いましたが、お聞きしましたところ、福岡市の「エンディングノート」の中には終活関連業者の広告が多数掲載されており、これらの広告収入によって印刷費用等を全て賄っていることに加えて、毎年約200万円の広告収入が市の歳入となっているとのことでありました。
このような他都市での取り組み事例も参考としながら、市民の皆さんが願う最期の迎え方を叶える「終活」と「ACP」の更なる普及啓発に取り組んで頂くことを要望して、質問を終わります。
#はだだいせん #波田大専 #日本維新の会 #札幌市議会 #北海道 #札幌市 #中央区 #平成生まれ #36歳 #子育て世代 #2児の父 #松下政経塾 #元ホクレン職員 #札幌旭丘高校 #行政書士 #社会福祉士 #終活 #ACP #人生会議 #終末期医療 #延命措置 #尊厳死 #エンディングノート
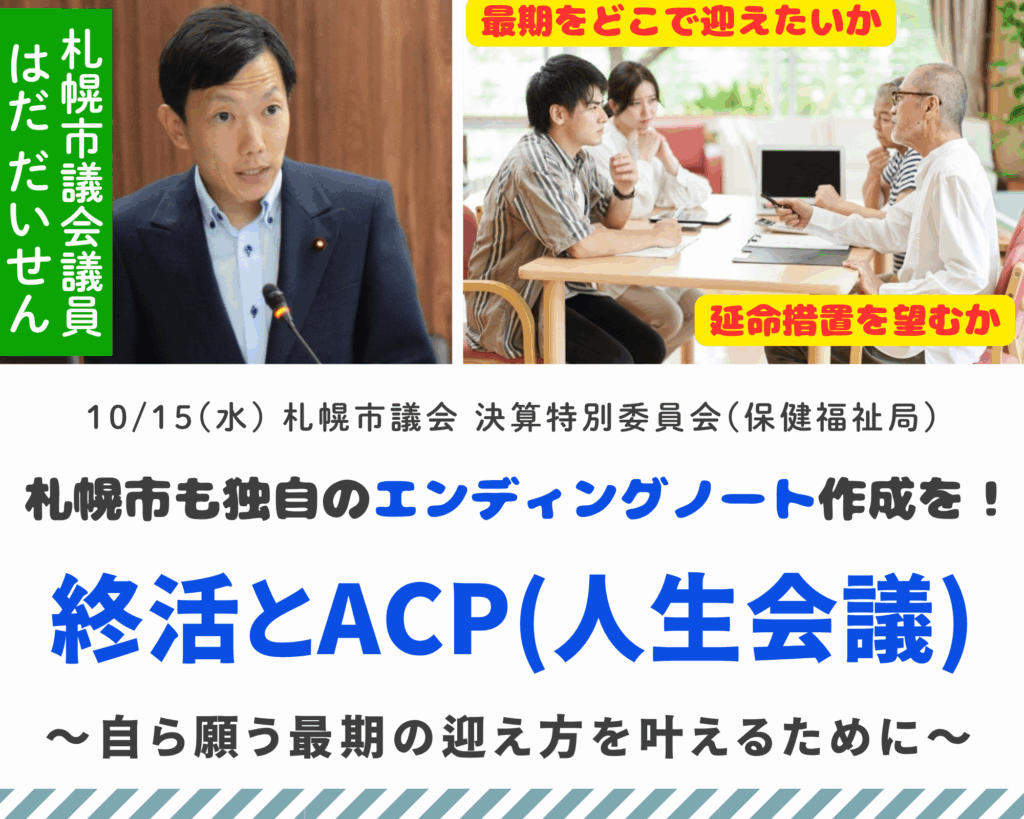
.png?1769458226)