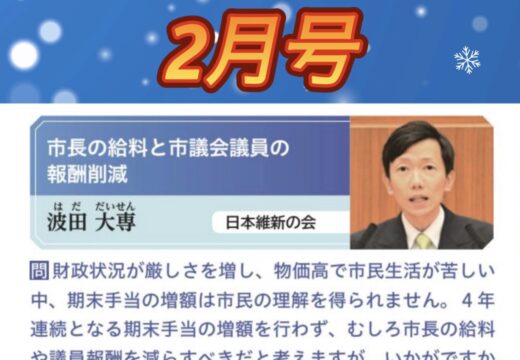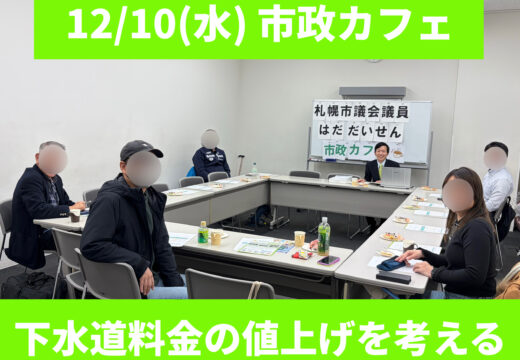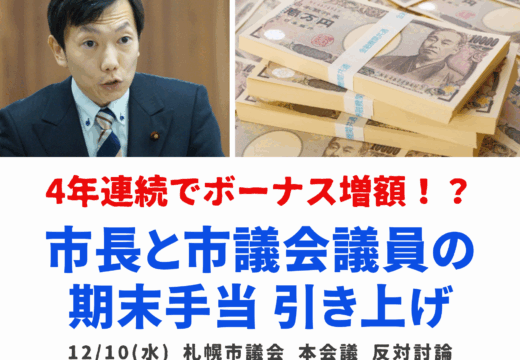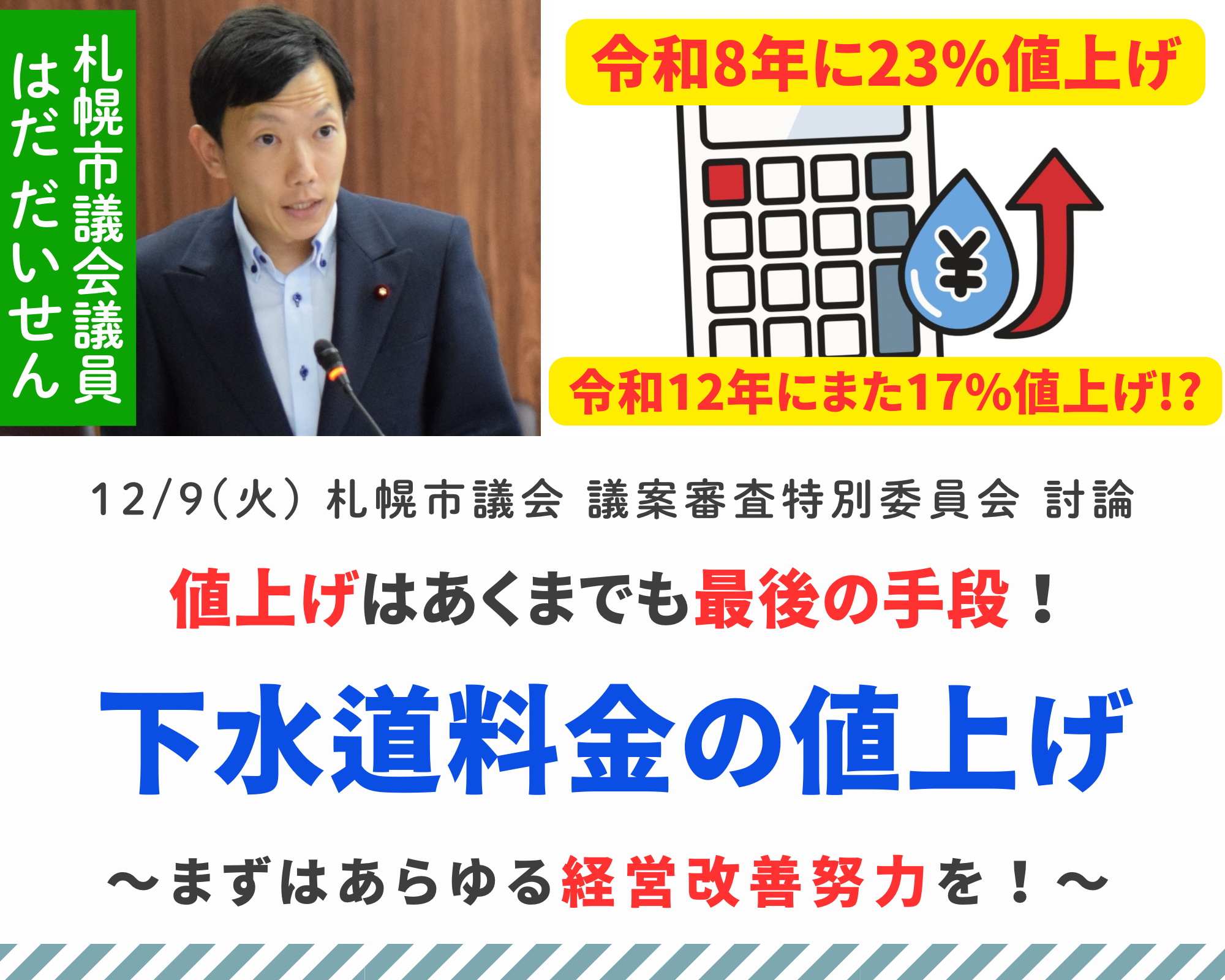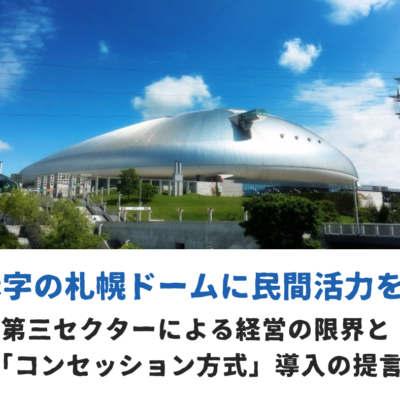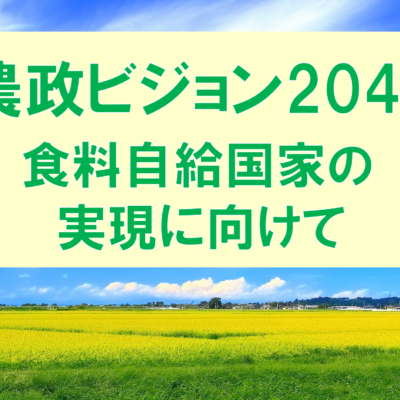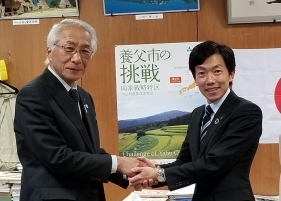4/26(土)、カナモトホールにて第11回目の「はだだいせん 市政カフェ」を開催しました。
今回は、「教育の無償化」をテーマに、現役の高校生2名や子育て世代の皆さま、公立高・私立高の教諭の方々、新聞記者の方、70代の方など、11名の皆さまにご参加頂き、それぞれのお立場から忌憚のないご意見をお寄せ頂きました。
また、現在、札幌市議会で審議が行われている陳情2件「子ども医療費助成の所得制限の撤廃」「放課後等デイサービスの所得に応じた負担額の見直し」の陳情者の方にもご参加頂き、陳情に至った経緯や切実な現状についても、お話頂きました。
「子ども医療費助成」は、今年度から札幌市においても対象が「高校3年生」にまで拡大されましたが、未だ所得制限がある現状です。
全国の政令市20市の中で、所得制限があるのは札幌市と広島市の2市のみとなっております。
「放課後等デイサービス」の利用者負担上限額は、生活保護受給世帯・市民税非課税世帯は「0円」、前年度の年間所得890万円以下の世帯は「月額4,600円」、890万円以上の世帯は「月額37,200円」と、高所得世帯においては、途端に負担額が8倍にも跳ね上がってしまう現状にあります。
他の政令市では、「福岡市:所得によらず一律3,000円」「神戸市:0円、1,700円、4,600円、13,600円、16,620円の5段階」「名古屋市:上限額1万8,600円の区分を追加」「京都市:上限を国区分の半分に軽減」「大阪市:兄弟の他制度利用状況により軽減」等、独自の負担軽減措置に取り組む動きがあります。
また、道内では、岩見沢市、美唄市、赤平市、三笠市、北広島市、士別市、根室市、網走市で「無償化」に取り組む動きがあります。
【陳情者の方の声】
・難病を持つ小学生の子どもがおり、通院しながら放課後等デイサービスを利用している。
・「子ども医療費助成」については、所得制限の年収を超えないように残業や休日出勤を抑える等、働き控えを行っている状況。
・生後1カ月で病気が早く見つかったからまだ良かったものの、所得制限によって受診控えが起これば発見が遅れ、手遅れとなってしまう可能性もある。
・「放課後等デイサービス」では、身体機能や言語の訓練を行っている。例えば、ペットボトルのキャップを開けたり、ペンを持ったり等、多くの子どもが普通にできることができなかったりする。社会に出てから困らないように、なるべく多く通わせてあげたい。これは学校に通うのと同様に、「教育」の一環であると考えている。
・多くの世帯が「月額4,600円で利用し放題」である一方で、高所得世帯だけ利用者負担上限額が月額37,200円と高額であるため、利用控えをしているとの声も多い。
・所得制限は、全ての制度において、概ね年収900万円前後に設定されており、このラインを少しでも超えた途端に、あらゆる負担を一気に強いられる現状がある。累進課税で高い税金を支払いながら、子ども医療費助成の対象から外れ、放課後等デイサービスの利用者負担額が高くなり、障害児が受け取れる手当ももらえなくなってしまう。
【子ども医療費助成・放課後等デイサービスの所得制限に関する主なご意見】
・「子どもの権利条約」では、「親の経済状況によって子どもを差別してはならない」と定められており、この条約に基づいて札幌市でも「札幌市子どもの権利条例」が制定されているが、所得制限はまさに「親の経済状況による差別」ではないのか。
・放課後等デイサービスの利用者負担については、せめて神戸市のように5段階に分けてはどうか。認可保育所の保育料(2歳児クラス以下)は所得に応じて15段階に分かれている。
・放課後等デイサービスについて、札幌市の場合、完全無償化するために必要な財源は4.7億円、福岡市のように利用者負担一律3,000円(月額)とするための財源は2.6億円。このくらいの財源を捻出できないのか。
・「札幌市誰もがつながり合う共生のまちづくり条例」が制定されたが、このような札幌市の現状は、共生のまちづくりの理念とあまりにもかけ離れているのではないか。
・鹿児島市では、放課後等デイサービスが完全無償化されていたが、財政難を理由に一部有償化された経過もある。
・放課後等デイサービスの施設が増え、利用者も増加していることは良いことでもある反面、受給者証の乱発も問題の1つ。本当にサービスの利用が必要な子どもであるのか、見極めが必要。事業者目線で見れば、程度の軽い利用者に多く集まってもらった方が人員配置も少なく済み、収益性も高い。
・以前に、稚内から札幌に引っ越してきた高校生が、稚内市では無料だった医療費が札幌市では有料であることに驚いていたが、本来は住んでいる地域によって差があるのはおかしい。やはり国が一律に制度化するべきではないか。
【高校授業料の無償化に関する主なご意見】
・私立高も無償化の対象として就学支援金を引き上げすると、私立は授業料を値上げし、結局は無料とならないことも想定される。
・授業料だけ無償化されても、教材費や修学旅行など、結局は負担しなければならない費用も多い、例えば、修学旅行は公立が10万円、私立は50万円とすれば、結局私立には通えない。
・商業の高校生には6,000円くらいの電卓を購入してもらっていたが、これも買えない家庭が多く出てきた。5~6万円のパソコンも買ってもらわないといけないが、買えない世帯のために学校がレンタル用にストックしておかなければならない現状。このような費用を、どこまで公費で賄うのかも重要。
・先進国の中でも、日本は教育における家庭の負担額が大きい。
・高校受験の制度にも問題があり、現状では公立は一発勝負であるため、公立に落ちてしまうと私立に行かざるを得ない現状もある。体調不良という不運な結果もある。
・部活を頑張りたくて、希望通りの公立高に入ったが、私立の受験時には胃腸炎で大変だったことが実際にあった。
・希望通りの公立高に入ったが、やはり授業料の面から公立しか見ていない面もあった。もし私立も無料であれば、もう少し真剣に私立高も見ていたかもしれない。
・公立高は特色を出しにくい。転勤もあって教員のモチベーションが上がらない面もある。私立の無償化による公立高の定員割れも問題視されているが、そもそも地区の中学が減少しており、既に定員割れが起こっている。
・国立大学(国大協)では、総合型選抜(いわゆるAO入試)の割合を3割にまで増やす方向性もあるが、そうなると私立が受験にも強い。公立離れも進むのではないか。
・札幌旭丘高校に新設された数理データサイエンス科は、定員割れが続いており、課題もあるように思う。そもそも、公立高の場合、このような方向性は誰が決めているのか。校長も数年で変わる。市や教育委員会も関わっているのか。責任の所在が不明。
・「高校授業料の無償化」は、何かを解決するための「手段」であると思うが、そもそも解決したい課題は何なのか。仮に、それが「親の所得によらない、機会の平等」であるとすれば、やはり高校授業料の無償化という手段では、その課題は解決されないのではないか。
・30年前とは違い、現代は夫婦フルタイムも多い。所得制限に引っかかるため、昇進を断る等の声も聞こえるが、これは労働力不足にも拍車をかけることであり、社会全体にとっても良くないのではないか。たしかに児童手当は昔は無かったが、一方で、昔はあった扶養控除が今は無い。子育て世代の負担は大きい。
#はだだいせん #波田大専 #日本維新の会 #札幌市議会 #北海道 #札幌市 #中央区 #平成生まれ #36歳 #子育て世代 #2児の父 #松下政経塾 #元ホクレン職員 #札幌旭丘高校 #行政書士 #社会福祉士 #教育の無償化 #市政カフェ
.png?1772094441)


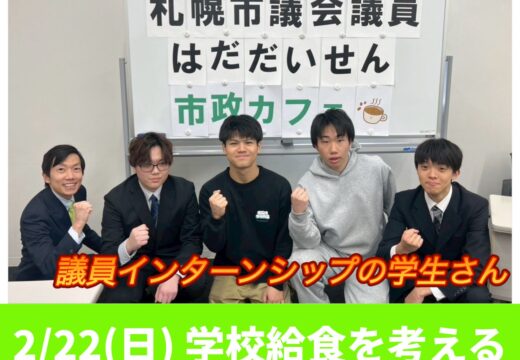

-520x360.png)